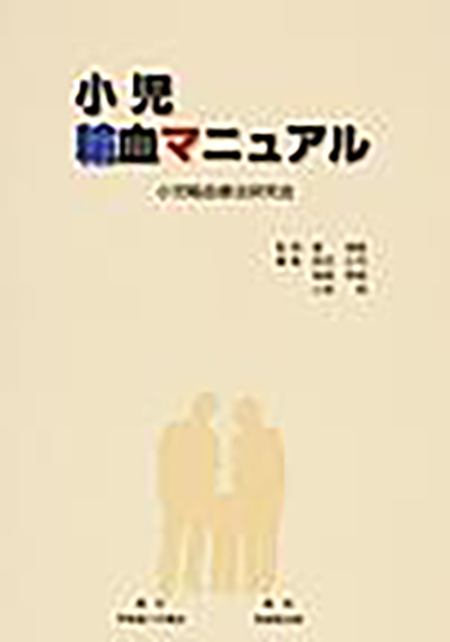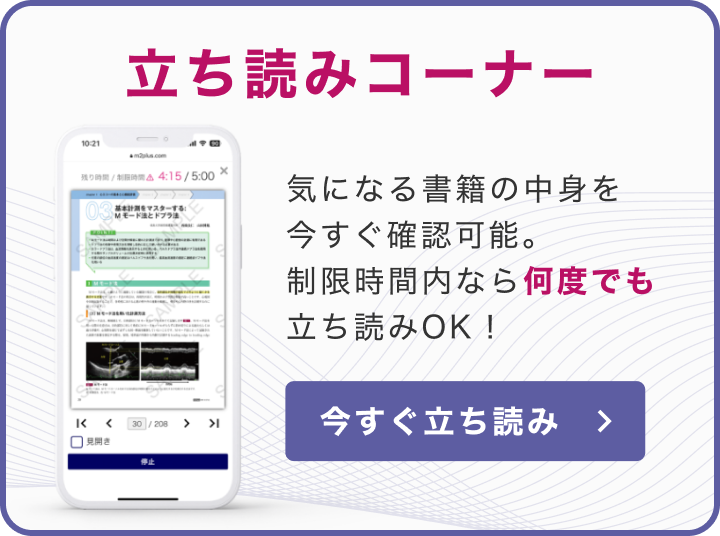- m3.com 電子書籍
- 宇宙堂八木書店
- 小児輸血マニュアル
商品情報
内容
小児輸血療法の問題点を再点検し今後の改善を目的として執筆された専門書。ベッドサイドで簡単に利用できるページ構成と、多くの図表で理解を深めます。新生児・小児科領域の医師、看護師、臨床検査技師の方にオススメです。
序文
出版の主旨(監修・編集者より)
小児輸血療法に関する出版物はそれほど多くない。従来より、小児の輸血については、使用頻度が少なく、使用量はさらに少ないため、大方の関心を引いてこなかったことが原因であった。我々は、清水 勝先生(元:東京女子医科大学輸血部教授)のご支援を受け、1992年に月本一郎先生(前:東邦大学小児科教授)を代表世話人として「小児輸血研究会」を発足させた。研究会の目的は、小児の輸血療法のあり方について、担当する各分野の臨床医と輸血担当者が、実務面を主体に検討し、合意を目指すことであった。
その活動は1994年第42回日本輸血学会総会(総会長:清水 勝先生)において小児輸血のシンポジウムが企画されたのをはじめ、2001年には「小児輸血療法」(監修:清水 勝、編集:月本一郎、星 順隆、長田広司)を出版し、10年間の蓄積を広く世に問い、小児医学に貢献できたと考えている。
2003年に「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(血液法)」が施行されるに至って、輸血医療の環境は大きく改善されてきた。さらに2005年に示された、「輸血療法の実施に関する指針」・「血液製剤の使用指針」第3版により、適正な輸血療法の方向性が示されものの、小児領域の輸血には多くの問題が残存し、いまだ改善に向けた活動が必要である。
私(星)が月本先生から代表世話人を引き継いだ後、第53回日本輸血学会総会(2005年:総会長:星 順隆)、第15回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム(2009年)等で小児輸血問題点を報告するなどの活動を続けてきた。しかし、研究会発足時からの世話人は、すでに、清水勝先生、月本一郎先生、白幡聡先生が退官され、さらに、西川健一先生、長田広司先生と私も現職の退官が目前にせまっている。
そのような時期に発足から20回目の集会(2008年)を開催したところ、前回の出版以後の変化を踏まえて、今日の小児輸血療法の問題点を再点検し、積み残した問題点を整理するとともに、今後の改善に寄与することを目的に、再度出版を企画することが世話人会で決定した。執筆は本会の世話人自身が担当し、対応が困難な部分のみ、研究会で講演を頂いた、その道のエキスパートの援助を頂くこととした。
本書は、ベッドサイドで簡便に利用できることを目指して、各項目を見開き2ページもしくは4ページ以内に収め、理解を助ける図表を多くすることに苦心した。さらに、可能な限り安価で出版できるように出版社にも協力を依頼した。新生児、小児科領域の医師、看護師、臨床検査技師の方々が、手軽に入手し、手元において利用していただけるものになったと確信している。
本書が、小児医療における輸血の安全性の向上に寄与することを願っている。
最後に、小児輸血療法研究会に参加し、積極的に討論して頂いた、各診療部門の先生方に感謝するとともに、小児輸血療法研究会の20年にわたる活動をサポートして頂いた、オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社に深謝する。
平成21年12月
監修 星 順隆
編集 長田 広司、堀越 泰雄、小原 明
目次
1.小児輸血療法の歩み
1) 小児輸血療法の特徴
2) 小児に対するインフォームド・コンセント(アセント)
3) 小児と輸血拒否
2.小児輸血を理解するための基礎知識
1) 輸血に関連する小児の生理機能
2) 輸血に関連する新生児期の免疫学的背景と疾患
3.小児に対する輸血手技
1) 検査手技
2) 機器と材料
4.小児疾患と輸血療法の実際
1) 新生児医療
2) 小児血液疾患と輸血
(1) 小児の貧血
(2) 悪性腫瘍と輸血
(3) 先天性出血性・血栓性疾患
3) 小児外科と輸血
4) 小児心臓外科疾患と輸血
5.特殊な輸血療法
1) 臍帯血輸血
2) 顆粒球輸血
3) 自己血輸血
6.細胞治療
1) 骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植
2) 造血幹細胞移植と輸血
3) 再生医療
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:12.8MB以上(インストール時:27.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:51.2MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:15.8MB以上(インストール時:39.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:63.2MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784771950665
- ページ数:70頁
- 書籍発行日:2009年12月
- 電子版発売日:2018年6月15日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:2
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcher(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。