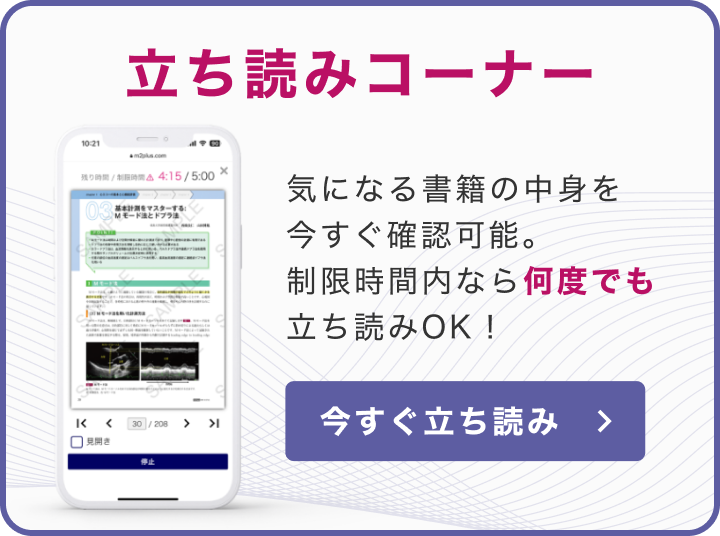- m3.com 電子書籍
- 改訂 ドクターヘリ ~救急医療用ヘリコプターの現状と救命医療システムのこれからを考える
商品情報
内容
初版の『ドクターヘリ』が2003年に刊行されてから20年が経過した。その間に、国の法律である「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」が成立・施行され、また航空法施行規則第176条(捜索又は救助のための特例)にドクターヘリが加えられるなど、ドクターヘリは救急医療において欠かせない存在となった。現在では、全国でドクターヘリの運航が年間3万件、安全に、円滑に行われ、多くの命が救われている。
序文
はじめに
平成15(2003)年12月に,初版の『ドクターヘリ』を上梓して,早いもので20年が経過した。その間に,国のドクターヘリの法律である「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」が成立,施行され,航空法施行規則第176条(捜索又は救助のための特例)にドクターヘリが加えられ,ドクターヘリの運航が,年間2.5 ~ 3万件,全国の都道府県で,死亡事故もなく,安全に,円滑に,行われるようになった。
このことから,川崎医科大学附属病院高度救命救急センターで初めて行われたドクターヘリの運航を,わが国の救急医療,救急医学教育を検討,評価しながら,救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)が,いかに発展してきたかを詳細に述べることは,お世話になった皆様への感謝の気持ちになるではないかと思ったので,当初はこれを『改訂ドクターヘリ』として上梓しようと思ったのであるが,内容が増加して,著者がまとめることが不可能と思われたので,著者のドクターヘリ導入の主目的であった,へき地・離島にも都会と同じ高度救急医療体制を提供して,へき地・離島の過疎化を防ぐという趣旨で,『ドクターヘリの全国展開と広域救急医療体制の構築』という冊子にして上梓した。しかし,著者の気持ちとしては,どうしても『改訂ドクターヘリ』として,川崎医科大学附属病院高度救命救急センターと日本の最初の救急医学講座としての医学教育を主体とした冊子を出版したいと思ったので,あらためて本書を『改訂ドクターヘリ』として出版することにしたのである。そのため,本書には前著と同じ図表,文章が含まれることとなったが,本書はドクターヘリ,救急医療,救急医学教育,日本航空医療学会での活動を中心にまとめたので,内容としては同じではないと著者は思っており,ご理解のうえご一読いただけたらと思っている。
また,川崎医科大学附属病院救急部の開設(北米型ER)は,昭和51(1976)年4月1日であり,令和8(2026)年4月1日には,救急部開設50周年,さらに,川崎医科大学におけるわが国最初の救急医学講座の開講は,昭和52(1977)年4月1日なので,令和9(2027)年4月1日には開講50周年を迎える。そこで,同窓会の幹事会で「本書を救急部開設50周年,救急医学講座開講の50周年の記念誌にしてはどうか」との話が出たので,本書を救急部開設・救急医学講座開講50周年記念誌にしたいと思ったので(現在の講座でも50周年の記念誌を出すのであろうが,著者がそれまで生きている自信がないので),本書を先に先に上梓することをご理解いただきたいと思っている。
今から40年ほど前の昭和56(1981)年10月23日に,わが国最初の救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)の実用化研究が,(社)日本交通科学協議会(現日本交通科学学会)の故冨永誠美副会長(元警察庁初代交通局長)の主催により1日だけ行われ,ドクターヘリの導入が「重症傷病者の救命と予後の改善に有効であることが,実証,認定されたのである(当時は,交通事故による死亡者が年間2万人に近づきつつあったのである)。その後,(社)日本交通科学協議会によるドクターヘリの実用化研究は,20年にわたって5回行われた。
平成13(2001)年4月1日に,内閣官房内閣内政審議室で行われた「救急医療用ヘリコプターの調査検討委員会」において,厚生省で行われた試行的事業での救急医療用ヘリコプターの導入が,重症傷病者の救命率の向上と予後の改善に有効であることが認められて,わが国最初のドクターヘリが,川崎医科大学附属病院高度救命救急センターに配備されたのである。そして,令和4(2022)年に香川県にドクターヘリが導入されたことによって,全国47 都道府県への配備がなされたのである(京都府にはドクターヘリ基地医療機関はないが,関西広域医療連合に所属しており,他府県の医療機関のドクターヘリのお世話になったときには,京都府として運航費用を出しているので,制度上はドクターヘリが運航されていることになっている)。ドクターへリが全国に配備されるのに,日本は,実に40年の歳月を必要としたのである。令和4(2022)年度には,年間36,434 件の出動要請があり,受諾件数は年間29,245 件,診療患者は年間22,892名であった。厚生省が行った試行的事業における救命率45.6%からみると,相当数の傷病者(患者)が救命されたことになるのである。
著者がドクターヘリの導入に専念するようになったのは,昭和54(1979)年に川崎医科大学に救命救急センターが配備され,県北の市町村から重症の傷病者が多数搬送されるようになったが,その多くが搬送途上で心肺停止となって来院することがきっかけであった。今の医学では,3分以上心肺が停止して脳に酸素が行かなくなると,いかなる治療を行っても,脳が再び回復し,普通の会話ができるようにはならない可能性が大きいのである。
医学,医療としては,当たり前の話であるが,重症であればあるほど,いかに早く医師による適切な救命治療が開始できるかが,傷病者(患者)の予後に大きく関与しているのである。救急車による搬送途上で,傷病者が心肺停止になるのは,救急業務として救急車で,長距離を長時間かけて医療機関(救命救急センター)に搬送されるからであり,このことは,岡山県だけの問題ではなく,全国のへき地・離島を有するすべての都道府県で毎日起こっている問題である。これらの傷病者を救命するためには,当時,欧米では当たり前のこととして行われていた,ヘリコプターに医師と看護師を搭乗させ,傷病者発生現場から医師による適切な救命治療を行わなければ,傷病者は救命されない。すなわち,医療を行う厚生労働省が“ドクターヘリ”を導入しなければならなかったのである。
そのため著者は,最初,救命救急センターを配備した厚生省(現厚生労働省)に行き,救急医療用ヘリコプターの導入を担当の指導課長(現地域医療計画課長)に会い,この話をしたところ,「そんなお金もない。法律もない,前例もない」とのないない尽くしであった。ここから,著者と関係者と国(厚生省,総務省消防庁,運輸省〔現国土交通省〕)との厳しい交渉が,始まったのである。結果として,ドクターヘリのための法律ができ,航空法施行規則第176条を改正して,ドクターヘリをこの法律の中に入れ,傷病者発生現場で医師による救命治療が行われるようになったのである。
このことは,傷病者の医療機関への搬送を厚生省ではなく,自治省消防庁の搬送業務にしたことで,重症傷病者は,早く医療機関に搬送しなければならないとの医療としての発想にならず,時間を要しても傷病者を医療機関に搬送すればよいとの単純な発想であったため,傷病者が搬送途上で心肺停止になっていたと想定されるのである。
欧米では,傷病者の搬送には医師が必ず関与しており,重症傷病者には「医師が搭乗した救急医療専用のヘリコプターが必要なのである」との発言があったので,欧米では1960年代から救急医療用ヘリコプターが導入されたのである。わが国では,ドクターヘリにより令和4(2022)年までに29万6,094名の重症傷病者が救命搬送されているので,厚生省の試行的事業で出された救命率46.5%から算出すると,少なく見積もっても10万人近くの重症傷病者がドクターヘリで救命搬送され,予後の改善を得ていることになる。少なくみて10% としても,1万人近くの傷病者がドクターヘリによって救命され,社会復帰と予後の改善を得ていることになる。年間でみると,毎年2 千人の傷病者が予後の改善を得たことになるのである。このことは,ドクターヘリの運営費以上のお金が,社会(国)に還元されていることになるのである。平成13(2001)年4月1日に,国としてのドクターヘリの運航が,川崎医科大学附属病院高度救命救急センターで開始されて以来,20年以上が経過し,死亡事故のない,安全運航が,当たり前のこととして毎日行われている。多くの関係者の忍耐と努力により,ドクターヘリが世に送り出された結果が,今日のドクターヘリの隆盛,人命救助に関与していることは,間違いのない事実であると著者は思っている。
著者のドクターヘリ導入時の信念は,「重症患者の救命治療を行う救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)に死亡事故がってはならない」ということである。幸いなことに今まで,航空機事故,医療事故による死亡事故は1件もないが,著者は,ヘリコプターの事故のほとんどは人為事故だと思っている。すべての関係者が,「人命救助を行うドクターヘリに事故があってはならない」という共通の認識と信念を持って,ドクターヘリの運航を行う限りにおいて,事故は起こらないと著者は思っている。
そのために著者は,一般人も参加できる日本航空医療学会主催のドクターヘリ講習会を毎年2回,運航関係者と医関係者が協力して開催し,安全運航に努力してきた。これまでに講習会は40回以上を数え,参加者も5,000名を超えている。この講習会を続ける限りにおいて,大きな事故は発生しないと著者は信じている。
ドクターヘリは今や,テレビドラマや映画にもなり,ドクターヘリが空を飛んでいると「あっ,ドクターヘリだ」と子どもが叫ぶほど一般化された。ありがたいことである。今では,ドクターヘリが空を飛ぶことは,当たり前のように思われているが,このような状況になるまでには,解決しなければならない多くの問題があったのである。しかし,多くの関係者の協力により,今日のドクターヘリの活躍がある,と著者は感謝している。
著者が,ドクターヘリ導入者の一人として述べておきたいことは,このドクターヘリのシステムは,医療人ではない警察庁で初代交通局長をされた故冨永誠美氏が,昭和40(1965)年頃から激増した交通事故による死亡者を,何としても助けたい(交通事故死を減らしたい)と思い,著者もまた,医師の責任としてへき地・離島の医療過疎地の国民の現場や搬送途上での死亡を減らし,都会と同様の高度医療を提供したい,という医師としての個人の願いが,今日のドクターヘリの隆盛に繋がっていると思うのである。公人である冨永氏は,執念をもって救急医療用ヘリコプターの実用化研究をされたが,この冨永氏の執念,熱意がなかったならば,民間人である著者が,このドクターヘリの実現に関与できなかっただろうと思うのである。多くの関係者の協力と援助があって,今日のドクターヘリの安全と活躍,隆盛があることを,忘れてはならないのである。特に,ドクターヘリの全国展開にドクターヘリの法律をつくり,さらに,財政状態が良くない道府県に地方交付税措置という総務省の補助金が得られるように尽力された,HEM-Net の国松孝次元会長(元警察庁長官),篠田伸夫現会長(元自治省消防庁次長)のお二人には,改めて感謝申し上げたい。
著者は,ドクターヘリがゼロからスタートして,全国に展開されるまでの経過をまとめ,その歴史書として本書を残したく思い,上梓した。なお,第4 章の「ヘリコプターの機能と構造」は,セントラルヘリコプターサービス株式会社の横田昌彦氏に執筆をお願いしたので,感謝申し上げたい。
ドクターヘリの安全運航のために,現場で毎日関与されている医師,看護師,消防関係者,運航関係者など,すべての関係者の皆様にも,この場を借りて改めて感謝申し上げたいと思う。また,本書の編集においては,へるす出版の佐藤枢前社長,斉藤浩司氏,佐藤貴氏にも大変お世話になった。皆様,本当にありがとうございました。
令和6年11月25日
川崎医科大学名誉教授(救急医学)
一般社団法人日本救急医学会名誉会員
一般社団法人日本航空医療学会監事・名誉理事長
元認定NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク副理事長
小濱 啓次
目次
第1章 ドクターヘリの歴史
I.総 論
1 ドクターヘリの始まり
1 冨永誠美氏と川崎祐宣氏の出会い
2 ドイツADAC の訪問
3 救急医療用ヘリコプターの実用化研究
4 厚生省によるドクターヘリの運航開始
2 日本の救急医療体制とドクターヘリ
1 日本の救急医療体制の変化
2 救急医学と救急医療
3 川崎医科大学救急医学講座の創設
4 大学病院としての救急医学講座
5 看護師の搭乗について
6 救急業務と救急医療の協力体制の必要性
7 ドクターヘリを救急医療に用いる原点
8 厚生省によるドクターヘリ予算案
9 ドクターヘリ調査検討委員会の創設
10 新しい病院前救急医療体制の構築
11 諸外国における現状と搬送途上における心肺停止事例
12 ドクターヘリ導入のための協力者
Ⅱ.各 論
1 ドクターヘリの導入に関与された個人
1 岡村正明氏
2 冨永誠美氏
3 川崎祐宣氏
4 国松孝次氏
5 篠田伸夫氏
2 ドクターヘリ運航の始まり
1 昭和55(1980)年以前におけるドクターヘリの運航
2 昭和55(1980)年以降におけるドクターヘリの運航
3 ドクターヘリ運航に関係した団体,省庁,学会等
1 社団法人日本交通科学協議会(現一般社団法人日本交通科学学会)
2 認定NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)
3 内閣官房内閣内政審議室
4 厚生労働省
5 一般社団法人日本航空医療学会
6 川崎医科大学
7 日本救急医学会
8 日本臨床救急医学会
9 日本病院前救急診療医学会
10 へき地・離島救急医療学会
11 総務省消防庁
12 国土庁
13 総理府警察庁長官官房交通安全対策室
14 関西広域連合
15 浜松救急医学研究会と浜松救急医療用ヘリコプター株式会社
16 メディカルウィング(医療優先固定翼機)研究運航事業
17 D-call Net(救急自動通報システム)
18 国際航空医療協議会(International Aeromedical Evacuation Congress;AIRMED)
19 ドクターヘリ基地病院連絡調整協議会
まとめ
Ⅲ.ドクターヘリ創設の流れ
第2章 ドクターヘリの基本とその運営
1 ドクターヘリとは
1 ドクターヘリの語源
2 法律に定めるドクターヘリとは
3 ドクターヘリの目的
4 ドクターヘリ施策の目標
5 日本航空医療学会によるドクターヘリの定義
6 ドクターヘリはなぜ必要か
2 ドクターヘリの効果
1 厚生省の試行的事業における効果
2 外傷におけるドクターヘリの効果
3 社会復帰による経済効果
4 ドクターヘリ救命の好事例
5 ドクターヘリ効果のまとめ
3 ドクターヘリと消防防災ヘリ
4 ドクターヘリの運営
1 公的運航と私的運航
2 対象とする地域のヘリポート調査
3 消防機関との協議
5 ドクターヘリ運営の実際
1 適切な運用管理と情報管理
2 運営に必要な人員,施設,設備
3 機体の消毒洗浄
4 ドクターヘリ用基地ヘリポートのあり方
5 使用ヘリコプター
6 ドクターヘリ出動基準
7 ドクターヘリの事故につながる状態
8 ドクターヘリ運営のための費用
9 ドクターヘリを用いた診療に関する診療報酬上の取り扱いについて
10 搭載医療機器,医薬品
11 ドクターヘリ運航会社の資格
12 搭乗者の保険,搭乗手当について
13 ドクターヘリ搭乗スタッフの教育
14 ドクターヘリと消防防災ヘリとの協力体制のあり方
15 高速道路におけるドクターヘリの活動
16 無線について
17 夜間運航について
第3章 ドクターヘリ運航に関連する法律
I.総 論
Ⅱ.各 論
1 航空法と航空法施行規則
1 航空法
2 航空法施行規則
3 航空法施行規則第176 条改正によるドクターヘリの運航について
2 ドクターヘリ特別措置法
1 ドクターヘリ特別措置法の制定とその意義
2 ドクターヘリ特別措置法成立の経緯①
3 ドクターヘリ特別措置法成立の経緯②
第4章 ヘリコプターの構造と機能
1 ヘリコプターの概要
1 ヘリコプターの歴史
2 飛行機とヘリコプター
3 ヘリコプターの分類,形式
4 ヘリコプターの規模
5 ドクターヘリで活躍するヘリコプター
2 ヘリコプターの飛行原理
1 揚力の発生
2 操縦操作と姿勢の制御
3 ヘリコプターの構造と機能
1 構造の概要
2 メイン・ローター(主回転翼)
3 テール・ローター(尾部回転翼)
4 エンジン
5 トランスミッション
6 胴体構造
7 電気系統
8 機内/ 機外との通信
4 ヘリコプターの性能と特性
1 飛行性能
2 安全性
3 機外騒音
4 機内騒音
5 振動と動揺
6 吹きおろし(ダウンウォッシュ)
7 飛行方式
8 制限・限界事項
9 その他
第5章 航空医学(Aviation Medicine)
1 ドクターヘリが高空を飛ぶことによって生じる環境変化
1 気圧の低下
2 低酸素症(低酸素血症)
3 減圧症
4 温度変化
2 ヘリコプターの飛行に伴う損傷の防止
3 飛行によって生じる各種症状と疾患
1 気圧の低下を原因とする疾患
2 航空機によって生じる各種症状と疾患
4 飛行によって生じる各臓器器官の変化
1 中枢神経系
2 感覚系(目,鼻)
3 呼吸器系
4 心血管系
5 消化器系
6 精神障害を有する患者
まとめ
第6章 事故の予防(ヒヤリ・ハット)
Ⅰ.総 論
Ⅱ.各 論
1 ヒヤリ・ハット,インシデント事例について
1 ヒヤリ・ハット事例(日本航空医療学会安全推進委員会による)
2 インシデント事例
2 アクシデント事例:ハードランディングによる機体損傷
第7章 諸外国におけるドクターヘリの現状
1 ドイツ
2 スイス
3 フランス
4 イギリス
5 アメリカ
6 オーストラリア
7 国際航空医療学会
(International Society of Aeromedical Services;AIRMED)
第8章 ドクターヘリと救急医療体制
1 救急医療(診療)体制の始まり
1 救急告示医療機関と救命救急センター
2 救急告示制度の問題点
3 大学病院はいかにあるべきか
2 救急医療体制にドクターヘリを導入する目的と始まり
3 新しい救急医療体制の構築
1 病院前救護の現状
2 搬送・受け入れルール
3 メディカルコントロール体制の確保
4 メディカルコントロール協議会の役割
5 救急医療機関の役割①
6 救急医療機関の役割②
4 わが国の救急医療体制の流れ
5 今後の救急医療体制のあり方
1 ドクターヘリの導入と広域救急医療体制の構築
2 救急医療体制の一本化
第9章 ドクターヘリと災害医療
1 災害におけるドクターヘリの必要性
2 災害時におけるドクターヘリの運航について
1 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
(平成19 年6 月27 日法律103 号)
2 航空法施行規則第176 条改正に伴うドクターヘリの運航について(通知)
3 大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針
(厚生労働省医政局地域医療計画課平成28 年12 月5 日)
4 防災基本計画の改定(平成30 年6 月29 日)
5 災害時における自衛隊の活動と「情報提供ノータム」の発出
6 HEM-Net の提言
3 災害医療に関連する法律
1 災害対策基本法(昭和36 年11 月15 日法律第223 号)
2 災害救助法(昭和22 年10 月8 日法律第118 号)
3 大規模地震対策特別措置法(昭和53 年6 月15 日法律第73 号)
4 過去の災害におけるヘリコプターの医療としての運用
1 雲仙普賢岳火砕流(長崎県)
2 北海道中央高速自動車道多重衝突事故
3 北海道奥尻島地震(北海道南西沖地震)
4 阪神・淡路大震災
5 東日本大震災
6 熊本地震
第10章 ドクターヘリとへき地・離島医療
1 へき地・離島になぜドクターヘリが必要なのか
2 へき地・離島医療の現状
3 へき地・離島対策はいかにあるべきか
4 へき地・離島医療に関連する法律,省令
第11章 ドクターヘリの現状と今後のあり方
1 ドクターヘリの現状
1 ドクターヘリの配備状況
2 ドクターヘリ現場出動における経過時間
3 ドクターヘリ運航実績の推移
4 ドクターヘリ傷病者搬送件数の推移
2 ドクターヘリの今後のあり方
1 広域救急医療指令センターの創設と消防機関との協力体制
2 ドクターカーの導入
3 固定翼航空機の導入
4 高速道路への離着陸について
5 夜間運航について
6 へき地・離島に夜間照明付き臨時ヘリポートの設営
7 消防機関と厚生労働省,日本医師会との新しい協力体制の構築
8 基地病院でカバーできない地域への新しい基地医療機関の創設
日本航空医療学会について
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.8MB以上(インストール時:29.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.3MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.8MB以上(インストール時:29.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.3MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784867190999
- ページ数:308頁
- 書籍発行日:2025年1月
- 電子版発売日:2025年1月28日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍アプリが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。