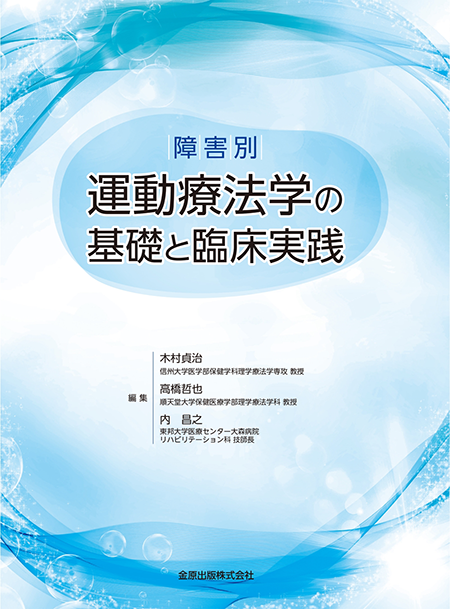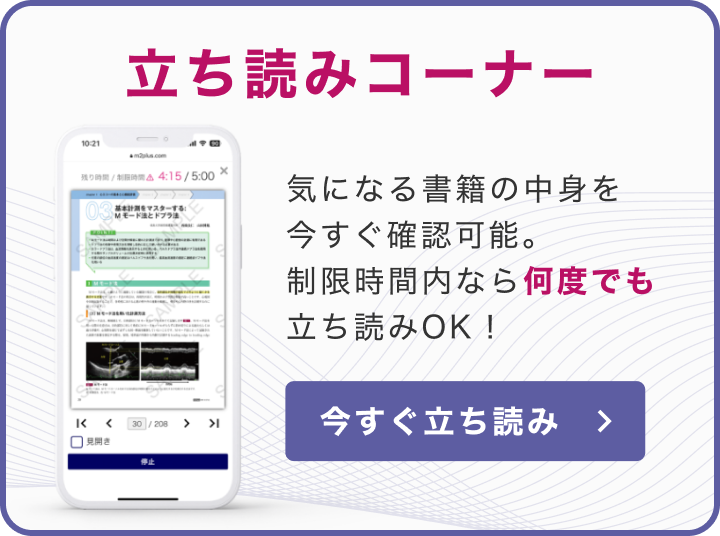- m3.com 電子書籍
- 障害別 運動療法学の基礎と臨床実践
商品情報
内容
各障害の運動療法に対し9つの共通項目を立てて網羅的に解説し、一部は動画で実際の動きを確認できるようにした。
著名な執筆陣により、理論や経験則、さらに最新のエビデンスを交えた実践方法を紹介。これから臨床現場に出る学生や新人理学療法士必読の書。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序
日常生活,仕事,趣味,スポーツ活動などを通して,人々がその人らしく生きていくためには,環境に適した身体の動作や運動が適切に遂行されることが重要となる。理学療法や作業療法の分野では,動作の障害や動作の構成要素となる要素的運動の障害の「予防」と「回復」を目的として運動療法が行われる。要素的運動となる単関節や複合関節における柔軟性,協調性,筋力,そして,合目的的動作である起居動作,歩行動作などの基本動作における安定性,協調性,速度性,持久性,応用性といった実用性の維持と改善を目的とした運動療法は,理学療法・作業療法において中核を成すものである。
運動療法の体系は,「疾患別運動療法」と「障害別運動療法」の2階層に区分されるが,本書では,これらのうちいろいろな疾患において共通性の高い「障害別運動療法」に焦点を当て,「基礎科学から臨床的実践技術」までを,わかりやすく,そして,系統的に学ぶことができるよう以下の4点に重点を置いて企画した。
1点目は,各障害の運動療法に関して,①基礎科学,②障害特性,③評価方法,④臨床判断の要点,⑤運動療法の基本的理論,⑥運動療法の臨床的実践技術,⑦運動療法のエビデンス,⑧予防的理学療法の意義,⑨研究の必要性という網羅的な共通項目を設け,個々の障害に対する運動療法の考え方や具体的な実践方法を系統的に学べるように工夫した点である。
2点目は,「知識として知っていること」と「実際に実施できること」とのギャップを埋めるために,上記の③評価方法や,⑥運動療法の臨床的実践技術の一部について,文章やイラストだけでは伝えられない“人の動き” や“治療技術の実際” を動画にて確認できるようQRコードを用いた動画配信サービスを提供するという点である。これにより,養成校の学生や新人セラピストの方々が,評価・治療の実際における所作を効率よく修得できるものと期待される。
3点目は,従来行われてきたような障害の改善を目的とした治療としての理学療法だけでなく,上記の⑧予防的理学療法の意義にあるように,超高齢社会の中で,いかにこれらの障害を予防するかという点について記述した点である。
4点目は,上記の⑦や⑨にあるように,運動療法の実践に関して,理論や経験則に基づいた紹介だけでなく,可能な限り最新で最良のエビデンスも交えて紹介するとともに,エビデンスが不十分な場合には,わが国の制度・文化・風土の下で行われたエビデンスを構築するための研究の必要性について言及した点である。このような学習を通して,わが国の理学療法や作業療法における根拠に基づく実践(evidence-based practice:EBP)の推進に寄与できるものと期待される。
本書におけるこれらの特徴を通して,既存の運動療法学関連のテキストとは内容的に異なった,新しいスタイルの運動療法学に関する情報を社会に発信することにより,養成校の学生や臨床現場の新人セラピストの方々が,“理” に根差した安全・効果的で科学的な運動療法の在り方を体系的に学び,人々の健康の維持・改善に寄与していただければ幸甚である。
最後に,上述した企画の趣旨を具現化するために,本書は,臨床現場や教育・研究現場の第一線でご活躍されておられるエキスパートの方々にご執筆いただいた。ご多忙の中,執筆にご協力いただいた皆様にこの場をお借りして心より感謝を申し上げたい。また,本書の発刊に向けて,企画から緻密な編集作業まで,粘り強く,そして,精力的に取り組んでいただいた金原出版の鈴木素子氏,芳賀なつみ氏に心より深謝したい。
2020年10月
木村貞治・高橋哲也・内 昌之
目次
第1部 運動療法学概論
1.運動療法の概念
1 わが国の理学療法の現状
2 理学療法の治療体系
2.運動療法の定義
1 既知の運動療法の定義
2 本書における運動療法の定義
3.運動療法の分類
1 運動療法の分類
4.運動療法の基本原則
1 運動療法の基本原則
5.病期に応じた運動療法の考え方
1 病期の理解
2 対象者の理解
3 病期に応じた運動療法の具体的な考え方
4 病期と説明と同意に関する留意点
6.運動療法における臨床推論の進め方
1 臨床推論とは何か?
2 臨床推論のプロセス
3 臨床推論におけるストラテジーと誤り
7.運動療法における根拠に基づく実践(EBP)の意義と進め方
1 運動療法におけるEBPの意義
2 運動療法におけるEBPの進め方
3 今後の展望
8.運動と栄養
1 運動における栄養知識の意義
2 リハビリテーション栄養とは
3 栄養の基礎知識
4 栄養アセスメント
5 運動時の栄養
6 運動と栄養療法(効果的な栄養摂取のタイミング)
9.運動療法におけるバイオメカニクス
1 バイオメカニクスの意義
2 体節の質量と重心
3 支持基底面と安定性
4 運動量と床反力
5 慣性モーメントと角運動量
6 関節運動のパターン
10.運動療法における運動制御と運動学習
1 運動療法における運動制御の意義
2 運動療法における運動学習の意義
3 運動療法との関連
11.運動療法における応用行動分析学の活用
1 なぜ,運動療法には応用行動分析学が必要か
2 応用行動分析学の基礎
3 運動療法のABC分析
4 応用行動分析学の活用
12.運動療法における安全管理
1 運動療法における安全管理の意義
2 安全管理とその考え方
3 感染対策
4 設備・環境整備
5 コミュニケーション
6 実施基準・中止基準
7 急変時・災害時の対応
8 患者情報ならびに個人情報の管理
第2部 障害別の運動療法の基礎と臨床実践
I.動作障害
1.起居動作障害
1 起居動作の基礎科学
2 起居動作の障害特性
3 起居動作障害の評価方法
4 起居動作障害の臨床判断における要点
5 起居動作障害に対する運動療法の基本的理論
6 起居動作障害に対する運動療法の臨床的実践技術
7 起居動作障害に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
2.歩行動作障害
1 歩行動作の基礎科学
2 歩行動作障害の障害特性
3 歩行動作の評価方法
4 歩行動作障害の臨床判断における要点
5 歩行動作障害に対する運動療法の基本的理論
6 歩行動作障害に対する運動療法の臨床的実践技術
7 歩行動作障害に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
II.機能・構造障害
1.関節可動域制限
1 関節の基礎科学
2 関節可動域制限の障害特性
3 関節可動域制限の評価方法
4 関節可動域制限の臨床判断における要点
5 関節可動域制限に対する運動療法の基本的理論
6 関節可動域制限に対する運動療法の臨床的実践技術
7 関節可動域制限に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
2.筋力低下
1 筋力の基礎科学
2 筋力低下の障害特性
3 筋力の評価方法
4 筋力低下の臨床判断における要点
5 筋力低下に対する運動療法の基本的理論
6 筋力低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 筋力低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
3.痛み
1 痛みの基礎科学
2 痛みの障害特性
3 痛みの評価方法
4 痛みの臨床判断における要点
5 痛みに対する運動療法の基本的理論
6 痛みに対する運動療法の臨床的実践技術
7 痛みに対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
4.随意性低下
1 随意性の基礎科学
2 随意性低下の障害特性
3 随意性の評価方法
4 随意性低下の臨床判断における要点
5 随意性低下に対する運動療法の基本的理論
6 随意性低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 随意性低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
5.協調性低下
1 協調性の基礎科学
2 協調性低下の障害特性
3 協調性の評価方法
4 協調性低下の臨床判断における要点
5 協調性低下に対する運動療法の基本的理論
6 協調性低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 協調性低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
6.筋緊張異常
1 筋緊張の基礎科学
2 筋緊張異常の障害特性
3 筋緊張の評価方法
4 筋緊張異常の臨床判断における要点
5 筋緊張異常に対する運動療法の基本的理論
6 筋緊張異常に対する運動療法の臨床的実践技術
7 筋緊張異常に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
7.バランス機能低下
1 バランス機能の基礎科学
2 バランス機能低下の障害特性
3 バランスの評価方法
4 バランス機能低下の臨床判断における要点
5 バランス機能低下に対する運動療法の基本的理論
6 バランス機能低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 バランス機能低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
8.全身持久力低下
1 体力の基礎科学
2 全身持久力低下の障害特性
3 全身持久力の評価方法
4 全身持久力低下の臨床判断における要点
5 全身持久力低下に対する運動療法の基本的理論
6 全身持久力低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 全身持久力低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
9.呼吸・循環機能障害
1 呼吸・循環機能の基礎科学
2 呼吸・循環機能障害の障害特性
3 呼吸・循環機能の評価方法
4 呼吸・循環機能障害の臨床判断における要点
5 呼吸・循環機能障害に対する運動療法の基本的理論
6 呼吸・循環機能障害に対する運動療法の臨床的実践技術
7 呼吸・循環機能障害に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
10.代謝機能障害
1 代謝の基礎科学
2 代謝機能障害の障害特性
3 代謝機能の評価方法
4 代謝機能障害の臨床判断における要点
5 代謝機能障害に対する運動療法の基本的理論
6 代謝機能障害に対する運動療法の臨床的実践技術
7 代謝機能障害に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
11.認知機能障害
1 認知機能の基礎科学
2 認知機能低下の障害特性
3 認知機能の評価方法
4 認知機能低下の臨床判断における要点
5 認知機能低下に対する運動療法の基本的理論
6 認知機能低下に対する運動療法の臨床的実践技術
7 認知機能低下に対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
III.その他
1.フレイル
1 フレイルの基礎科学
2 フレイルの障害特性
3 フレイルの評価方法
4 フレイルの臨床判断における要点
5 フレイルに対する運動療法の基本的理論
6 フレイルに対する運動療法の臨床的実践技術
7 フレイルに対する運動療法のエビデンス
8 予防的理学療法の意義
9 研究の必要性
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:40.7MB以上(インストール時:99.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:162.8MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:40.7MB以上(インストール時:99.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:162.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784307750608
- ページ数:580頁
- 書籍発行日:2020年11月
- 電子版発売日:2023年3月16日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。