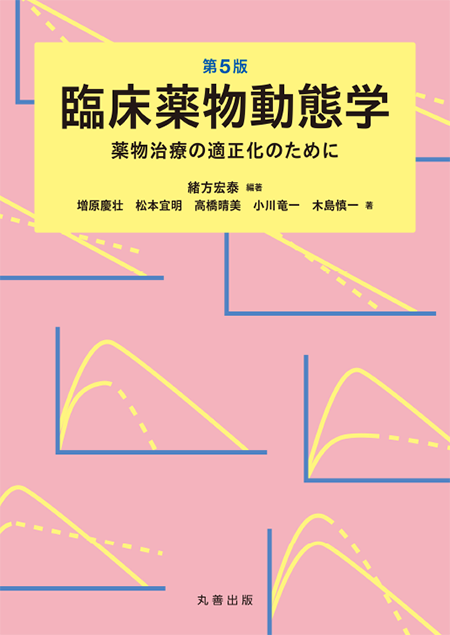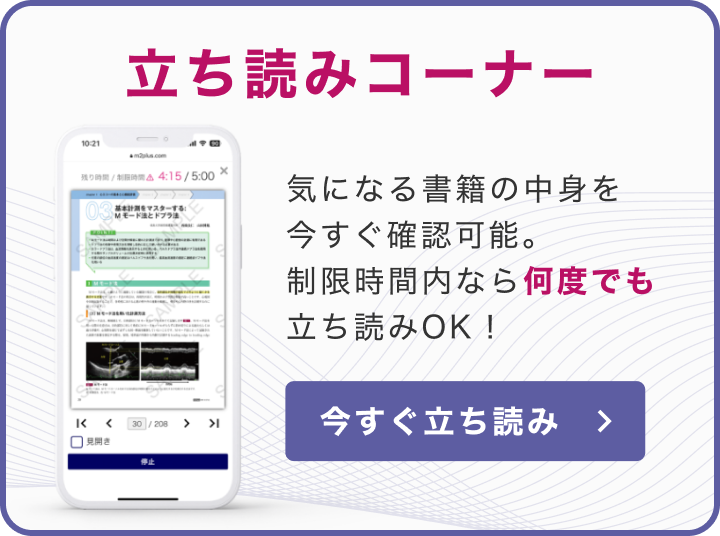- m3.com 電子書籍
- 丸善出版
- 第5版 臨床薬物動態学
商品情報
内容
薬物動態学を適正な薬物治療や合理的な新薬開発などに役立てるには、理論と実務の橋渡しをする手法が求められる。本書では、薬物動態の基本パラメータから血中薬物非結合形濃度の変化を推定する手法を解説。血中薬物濃度の頻回の測定も解析ソフトも必要とせずに様々な薬物の体内動態の特徴を把握できるようになることを目標とした。
理論の基礎からベッドサイドでの具体的な適用例までをコンパクトにまとめてあり、薬物動態学への理解を深めるのに最適な教科書である。
本書の特典として、国内で臨床的に利用可能な薬物に関する情報や便利なツールをwebサイト上で公開している。
・PKパラメータの特徴づけの結果、変動因子と病態変化に伴う動き
・各薬物の病態変化に伴う血中総濃度・非結合形濃度の時間推移(投与ルート別)
・PKパラメータの特徴づけを自身で行える計算用ファイル(Excel形式)
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
第5版 はじめに
薬物の体内動態というと,薬物血中濃度を用いて,式を多用しコンピューターで解析する小難しい学問といったイメージをお持ちの方も多いかもしれません.しかも,そのように難しくても臨床で薬物治療を行っていくうえで不可欠であれば,誰もが我慢してその内容を勉強したり,理解したりすることに取り組むと思われます.しかし,残念なことに臨床的有用性が十分明らかにされてきませんでしたので,臨床における認識は強いとは言えないことは率直に認めざるを得ません.本書を通じて,薬物血中濃度をいかに解析するかではなく,薬物治療に関わる薬剤師や医師が,薬物動態の情報をいかに治療に適用,利用していくかを述べることにより,薬物動態の視点が薬物治療を適正に遂行していくうえでいかに大切であるかを伝えたいと思っています.
薬物動態とはコンパートメントモデルを基本にした薬物血中濃度の時間推移の解析を中心としたものという印象を強く与えていたと思います.1−コンパートメントか2−コンパートメントかが興味であったり,吸収速度定数がどうだ,消失速度定数がどうだが興味の対象であったり,または,そのようなパラメータをつかった血中濃度の推定値が実測値と一致しているとか一致していないとかが興味の対象である場合には,確かに臨床的有用性は出てきません.しかも,対象とする患者はその病態を変化させていきますが,そのつど薬物血中濃度を取り直さなければ状態を把握できない,推定できないようでは,有用性は出てきません.変化に対応できることが有用性を決定します.現状の表現だけの機能では臨床応用は限定されてきます.これが,旧来のコンパートメントモデルを基本とする薬物動態学の大きな限界であったと思っています.ですから,何となく好き者が取り扱うもので,一般の臨床での実務者には関係がないものという感想も,そう誤ってもいないと思っています.臨床において薬物治療をフォローしていくための薬物動態学に変身させる必要を日ごろ痛切に感じていました.
私が臨床適用のための薬物動態を模索しているとき,大きな影響を受けた書が二つあります.
その内容をご紹介しながら,私が担当した章の内容紹介もしたいと思います.一つはRowland &Tozerの“Clinical Pharmacokinetics Concept and Application” でした.その書を手にし,その内容を読み始めたとき,感動を覚え,引き込まれ,一気に読んでしまったことを今もよく覚えています.これだと思いました.薬物の体内での動きと患者の生理的,病理的変化との関連を明確にできる体系,コンセプトが式の利用を最低限度に抑えて展開されていました.Rowlandらは,解析のテクニックではなく,考え方の神髄(Concept)を伝え,薬物血中濃度の変化を推定することに大きなウエイトを置いていました.その内容を十分理解し,具体化し,私の言葉で伝えることができるようになるまでには長い試行錯誤の繰り返しが必要でした.研究室で教官と大学院生による輪読を繰り返すことによって理解を深めていきました.私が代表幹事をお引き受けしている「治療薬物モニタリング研究会」における毎年の特別ゼミでの講義にその内容を反映し,受講生の反応や意見を組み入れてきました.また,明治薬科大学では1993年から大学院に臨床薬学専攻を設け,「薬物治療に判断力を有し,薬物治療が適正に行われるための責任の一端を担える薬剤師の養成」のための教育を開始しましたが,臨床薬物動態学の講義において全面的な展開を試み,やはり,学生や聴講生の反応を確かめながら講義内容を改善してきました.また,学生が研修中に見つけたり対応した症例を対象とする薬物治療の検討においても薬物動態の概念を具体的にどう適用するかについて学生とともに勉強を続けてきました.その内容を本書で論述したいと思っています.
薬物血中濃度の測定値を全く必要とせず,薬物動態の基本パラメータである,バイオアベイラビリティ,分布容積,全身クリアランスに,さらに尿中排泄率および血漿遊離形分率の五つの情報から,薬物の治療効果の背景となる薬物の血中遊離形濃度の変化を推定し,臨床イベントの把握に役立てることを目的としました.また,この視点は,臨床開発に参加される研究者にも是非つけていただきたいと願っています.患者に投与された新薬が示す臨床上のイベントを的確に見つけ出し,さらに的確な解釈,評価を行うためには,どうしても対象とする新薬の動態上の特徴をあらかじめとらえておく必要があるからです.なお,疾患時の薬物動態を中心に具体例を示すべきでしたが,枚数の制限から全くできませんでした.おこがましいようですが,私が尊敬する慶應義塾大学名誉教授加藤隆一先生の名著である「臨床薬物動態学」(南江堂)を是非お読みになることをすすめます.文献例が豊富に収載されており,私が本書において述べました考え方の確認のために,また,それを豊富化されるのに大いに役立つと思います.
私が影響を強く受けたもう一つの書はWinterの“Basic Clinical Pharmacokinetics” です.薬物血中濃度を利用した投与設計の考え方と応用が述べられています.症例をもとにした演習が多く,臨床の中で遭遇する典型的な症例に対応する考え方を習得させることが目的になっているものです.米国における臨床薬学教育用のテキストの一つです.私がその書を見たとき,これにも感動を覚えました.臨床適用の考え方を読み取ることができたからです.我が国では,薬物血中濃度を用いた解析といえば,精密な解析以外にはありませんでした.臨床から得られた情報量が少ない場合にも,精密な解析をなぞろうとする傾向が強くありました.しかし,医薬品の適正使用に具体的に関与しようとするとき,改めて,臨床応用,臨床適用という目的を明確にして,そのための概念と投与設計に必要な関係式を明確にする必要性を感じてきました.Winterの考え方に学びながら,本書では実践的な視点から投与設計のために必要な関係式をまとめ直しました.また,その背景となる考え方をできるだけ具体的に示すことを心がけました.
本書はさらに,増原先生,松本先生にも分担執筆をお願いしました.増原先生は早くからベッドサイドで薬剤師として薬物治療に関与してこられた我が国におけるパイオニア的存在の先生です.私が現在,代表幹事をしております「治療薬物モニタリング研究会」が発足したときの主要なメンバーの一人でもあります.常に薬物治療に関わる視点を明確にして活動をされてこられました.我が国の薬物血中濃度を用いた薬物治療のモニタリング,いわゆるTDMが血中濃度ありきで患者の治療のフォローという目的から遊離する傾向が強くなっていくことには強い危惧を持たれてきました.その点では,編者である緒方との視点は一致していました.そこで,増原先生には,とくに薬物血中濃度の測定値を利用して評価すべき薬物と状況および具体的な対応を,症例をもとにした演習という手法で解説していただくことを依頼しました.しかし,具体的な内容になりますと,臨床の場での実践の中で築き上げられてきた視点や内容と私が示した具体的な関係式などとの食い違いが一部に生じましたが,十分な討論を経て,全体的には統一性のとれた内容に仕上げることができたと考えています.一方では,逆に増原先生の主張点が十分出していただけず,中途半端になった部分もあるかと思いますが,それは一途に,編者である緒方の責任です.
松本先生は,薬物動態の分野では新進気鋭の研究者,教育者であり,終始,薬物治療と薬物動態の接点を追及されてきております.「治療薬物モニタリング研究会」の幹事を一貫してお引き受けいただき,その発展のために力を尽くしてこられました.とくに最近の松本先生の関心は臨床においてPK/PDのモデリングを具体化し,合理的な用法・用量の設定を行うことに置かれています.私が分担した章では,薬物の作用に関しては作用部位の薬物遊離形濃度に比例するというイメージのみにとどめてその薬物遊離形濃度の変化を推定することに力点を置きました.松本先生には,薬物の作用の強度の変化を主眼において,薬物血中濃度との関連を論じることを依頼しました.PK/PDのモデリングは現在欧米では最も注目され,研究も盛んな分野です.しかし,本書の目的は,薬物治療のモニターを行うための情報を明らかにし,その利用方法をできるだけ具体的に読者に示すことに置いているため,いわゆる精密な記述や解析を目的としたモデリングを述べることは本書の趣旨からは外れます.その点に関し,編者である緒方と松本先生の間で随分討論をし,認識を一致させました.しかし,PK/PDの分野がまだまだデータと検討の蓄積が必要である状況にあるという背景上の制約もあります.今回の松本先生に分担していただいた章の内容は,薬物の血中濃度と作用部位濃度の間に平衡が成立した相での関係と成立していない相での関係が一部混在しており,薬物治療に関わる薬剤師や医師が患者のモニターに用いるための視点から,概念を完全に整理し直すことや具体化する必要のある部分が残っているように思われます.松本先生には今後の重要な課題の紹介,問題提起として執筆いただいたものであり,是非今後の課題として学んでいただきたいと思います.
我が国における薬物治療のあり方が根本から問われていますが,当然,従来の薬物治療に関連した学問体系もその内容が問われていることになります.薬物動態の概念においても臨床における薬物治療に具体的に応用していくための展開に不十分さがあったと感じています.そのため,臨床適用に徹した概念を提起することを本書の目的としました.一貫した考え方によって貫かれた内容にすることが命題となりました.また,本書は,できるだけわかりやすく,不必要に式は用いず,概念で内容を伝えたいという趣旨から,各著者が聴講者を前に講義を行っていることを想定して執筆をすることにしました.このような経過から,一般の教科書というものとはかなり異なったものとなりました.
最後に,以上のようなかなりわがままな執筆方針を受け入れていただき,出版にまでこぎつけていただいた丸善 株式会社に深謝いたします.また,私たちの原稿の遅滞と戦い,最後まで叱咤激励をいただき編集に当たっていただきました,第三出版部 田島牧子さんに厚く感謝いたします.
2023年6月
緒方 宏泰
目次
第I部
A 血中薬物濃度のとらえ方
A1 薬物治療の適正化と薬物動態の関連性
A2 薬物動態の基本パラメータ
A3 薬物動態パラメータの変動要因からみた薬物の特徴づけ
A4 血中薬物濃度の決定
A5 薬物動態パラメータ値の収集
B おもな疾病における薬物動態変化の推定の考え方
B1 肝疾患における薬物動態
B2 心疾患における薬物動態
B3 腎疾患における薬物動態
C 薬物の投与設計に必要な関係式
C1 薬物投与後の血中薬物濃度を表現する関係式
C2 クリアランスが薬物濃度依存性を示す薬物の投与設計に必要な関係式
C3 薬物投与設計の考え方
C4 ベイズ推定を用いた血中薬物濃度の推定
第II部
D TDMの実際
D1 ジゴキシン
D2 ジソピラミド
D3 テオフィリン
D4 抗てんかん薬
D5 アミノ配糖体系抗生物質
D6 バンコマイシン
D7 その他
第III部
E PK/PD解析
E1 導入編
E2 基礎編
E3 応用編
第IV部
F 薬物の動態パラメータ値の特徴づけとその臨床応用
F1 薬物の体内動態パラメータ値とその特徴づけ─病態変化に伴う血中非結合形濃度の予測への応用
F2 Microsoft Excelを利用した薬物動態学的特徴把握のための数値計算
付表 薬物動態パラメータ
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:14.5MB以上(インストール時:37.7MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:58.0MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:14.5MB以上(インストール時:37.7MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:58.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784621308295
- ページ数:244頁
- 書籍発行日:2023年7月
- 電子版発売日:2023年7月10日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。