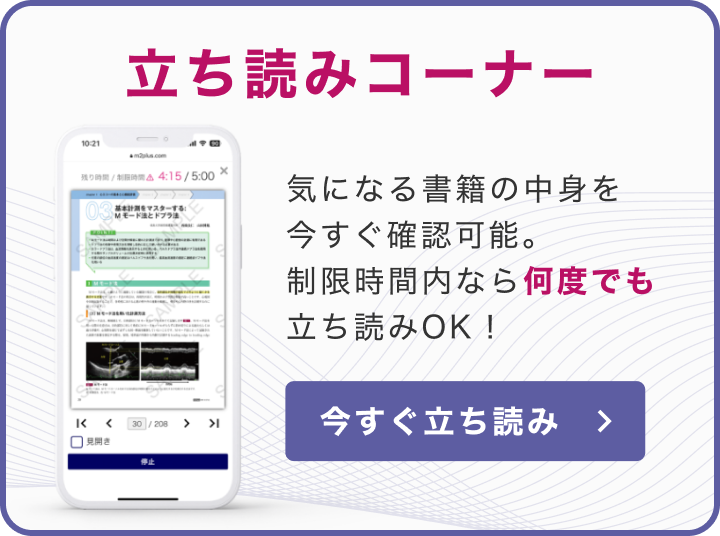- m3.com 電子書籍
- 宇宙堂八木書店
- 臨床検査の正しい仕方ー検体採取から測定までー
商品情報
内容
“検査前の注意事項”を取り上げ、何故そのように注意しなければならないのか等、系統的に整理し簡潔にまとめています。臨床検査関係者は勿論、各科医師や看護師、保健師、管理栄養士の方々にもオススメの一冊。
序文
発刊にあたって
臨床検査医学とは,血液,尿など生体成分を測定し,その検査データを科学的に分析することで,予防・臨床的な診断や治療方針決定の判断材料として提供する学問である。病気の診断・治療は太古の昔から行われており,長い間それは経験のみに基づくものであった。このような医療に科学的な色彩を導入したのが臨床検査である。ヨーロッパの有名な化学の指導者であるウプサラ大学のBerzelius の影響など臨床検査の誕生の背景にはいろいろあるが,臨床検査学体系確立の大きな要因の一つにFölling によるフェニルケトン尿症の解析がある。オスロの病院検査部所属の医師であったFölling は,知的障害の少女の尿からフェニルピルビン酸の結晶を見出し,フェニルアラニン代謝異常と病態との因果関係を明確にした。Fölling のこの仕事は,患者の血液や尿を分析することで病気の本態を突き止めることができる実例を示した点で意義がある。以後,病気の診断を経験に加えて臨床検査を用いることが行われるようになり,現在では,臨床検査データがないと,診断や治療指針決定に大きな支障が出るのが現実であり,医療における臨床検査医学の役割は大きくなってきた。
患者自身が訴える症状(主訴)は診断・治療にたいへん有効であるが,時に,客観性に欠けることがある。それに対して,科学的に分析された臨床検査データは客観的な指標として利用できるので,患者の診断や治療指針の決定にひろく用いられるようになっている。治療指針の決定や変更は検査結果の変動を参考にしてなされる。しかしながら,多くの要因が測定結果に影響を及ぼすので,それらを考慮せずに検査を行うと正しい検査が出来ない。このような影響因子としては,患者に投与されている薬物の影響などだけでなく,測定しようとする項目の生理的変動や測定法の違いなどがある。このように,測定結果に影響を与える様々な要因を検査前の注意事項(プレアナリティカル要因:preanalytical factors)と言う。これらの検査前の注意事項やそれに対する対策については,実際に検査を行っている臨床検査技師や臨床検査関係者は比較的良く認識しているが,医師や看護師には必ずしも充分な認識がない。このような注意をしないで,検体を検査部に提出したり,その結果を鵜呑みにして検査結果を解釈すると誤った診断や治療を行うことになる。
血液などの検査材料は,適切に採取され測定されないと検査結果の正しい解釈はできない。また,検査結果が同一個人であっても,おかれている状況で変動したり(個体内変動),個体差(個体間変動)があることは徐々に知られるようになってはきているものの,性別や年齢による違いなど非常に典型的なもの以外はまだ充分には認識されていない。
患者の状態を経過観察するときには,一連の検査結果の中から意味のある変化を見つけ、また,微妙な変動でも患者状態の変化を反映しているものであれば的確に認識し対処しなければならない。このためには,測定が精密で基準化されていることが大前提ではあるが,それだけでは不充分であり,検査結果に影響を及ぼす様々な要因を考慮して患者状態の変化を把握する必要がある。
測定結果に影響を及ぼす"検査前の注意事項"を整理して認識することは非常に大切である。本書は,そのような"検査前の注意事項"を取り上げ,何故にそのような注意をしなければならないのか,それらの注意を怠ったら,その結果,どのように検査データに影響が及ぼされるのかなどについて,系統的に整理し簡潔に纏め挙げている。医療関係者にとって大変役に立つ本である。また,2008 年4 月より,40 歳以上75 歳未満の方に対する「特定健診・特定保健指導」が義務づけられた。そこで,第7 章として「特定健診における検査前精度管理の在り方」を掲載したのでご活用頂きたい。
検査部や臨床検査に関係がある検査関係者は勿論のこと,多くの医療関係者がこの本を読まれることを願っている。
なお,本書は1996 年にWalter G. Guder, Sheshadori Narayanan, Hermann Wisser, BemdZawta 先生らが共同で出版された"Samples: From the Patient to the Laboratory"の翻訳本(正しい検査の仕方:検体採取から測定まで(訳:濱﨑直孝,濱﨑万穂))を参考にして,日本の臨床検査の専門の先生方に最新の情報をご執筆頂いた。また,本書刊行に際し,日本ベクトン・ディッキンソン株式会社およびBecton Dickinson and Company, USA の協力を得たことに謝意を表する。
平成20 年6 月
編者
濱﨑 直孝
高木 康
目次
発刊にあたって
第1章 生理的変動因子
1. 生理的変化:避けられない変動
A. 年齢による変化
B. 性別による変化
C. 妊娠による変化
2. 生活習慣による変化
A. 食べ物の影
B. 筋肉運動による変化
C. 高地による変化
3. 嗜好物による変化(カフェイン, 喫煙, アルコールなどの影響)
A. カフェインの影響
B. 喫煙の影響
C. アルコールの影響
4. 薬物の影響
第2章 検体採取
1. 検査をするタイミング
A. 日内周期の影響
B. 月経周期の影響
C. 食事の影響:なぜ食後 12 時間後に採血するのか?
D. 診断や治療行為と検査のタイミング
2. 輸液治療中のサンプリングはどうするか
A. 検査結果に影響をおよぼす診断と治療行為
B. カテーテルからの検体採血
C. 精神的ストレス
3. 採血時の姿勢や駆血帯による測定値の変化
A. 採血時の姿勢
B. 駆血帯の影響
4. どこから採血するか
A. 静脈採血
B. 目的に応じた採血の仕方
C. 採血量の決定
D. 動脈採血
E. カテーテルによる採血
F. 皮膚からの採血
5. 検体の取り違い防止
A. 患者・検体・検査情報を適切に認識するには
B. 検体を識別する方法
C. 検査室での流れ
6. 特殊の検体:髄液の検査
A. 使用する機材
B. 穿刺部位
C. 採取量
D. 髄液採取中の検査
E. 髄液採取に当たっての注意点
F. 髄液の保存と運搬
G. その他の注意点
7. 尿や唾液の検体
A. 尿の検体
B. 唾液の検体
8. 血清と血漿の違い,分離に際しての注意点
A. 血清と血漿での違い
B. 血漿が血清より都合がよい点
C. 血漿が血清よりも不都合な点
D. 血清(血漿)分離に際しての注意点
E. 血漿の種類
9. 添加剤と採血管の識別
A. 添加剤と採血管キャップの色分けによる識別
B. ヘパリン(硫酸化 D-グルコサミン,D-グルクロン酸,L-イズロン酸からなるムコ多糖体)
C. EDTA 塩
D. クエン酸
E. 解糖系の阻害剤
F. 細胞の保存
第3章 検体受領,搬送,受付および仕分けと保管
1. 検体の搬送時間と温度の影響
2. 一次検体の受領プロセス
3. 一次検体採取場所から検査室までの検体搬送プロセス
4. 検体の搬送方法
5. 検査室での検体受付および仕分け
6. 検体の保管要件
第4章 分析のための検体の準備
1. 血液検体が検査室に届いた後の処理:血清分離・分注・搬送・測定
A. 血清分離
B. 分注・搬送
2. 検査の進捗状況
A. ターンアラウンド時間
B. 検査室のロボット化
3. 検査室の安全基準:検体・試薬の廃棄,注射針・検体容器の処置
A. 注射針などの処理
B. 検体の処理
C. 試薬の廃棄
第5章 注意点
1. 輸血検査
A. 輸血の管理体制
B. 患者と輸血用血液の確認
C. 輸血検査の正しいやり方
D. 輸血用血液の保管法
E. 輸血を行う直前に確認すること
2. 凝固検査用の採血
A. 凝固検査用採血
B. 抗凝固剤の濃度
C. 抗凝固剤と血液の比率
D. 検体の採血
E. 検体の運搬
F. 検体の保存
G. 線維素溶解(線溶)活性の測定と血栓溶解療法のモニタリング
3. 血液検査用検体
A. 抗凝固剤は何を用いるか?
B. 抗凝固剤と血液の混合比
C. 採血と採血後の処理
D. 検体の運搬・保存・安定性
E. EDTA依存性偽血小板減少症
F. 血小板因子測定の注意点
4. 生化学検査(測定系が持つ問題点)
A. ドライケミストリーの問題点
B. 除蛋白の有無で測定結果が違う
C. 脂質の容積排除効果
D. 全血でのグルコース濃度と血漿でのグルコース濃度
E. 電解質(Na+,K+,Cl-,HCO3-)
F. 微量成分
G. 脂質
H. 一般的注意
5. 免疫化学検査
A. 免疫・血清検体の採血,保存,運搬
B. 採血の体位とタイミング
C. 薬剤の影響
D. 溶血の影響
E. 唾液や角層の混入
F. 冷蔵か冷凍か?
G. 抗凝固剤
H. 蛋白質分解酵素阻害剤
I. 補体活性
J. 副甲状腺ホルモン関連ペプチド
K. カテコールアミンの例
6. 細胞情報から得られるもの
A. 末梢血から血液細胞(白血球)の分離
B. リンパ球分離法
C. 血液細胞の分離と血球の保存におよぼす抗凝固剤と添加物の影響
D. 溶血法による血液細胞の分離:フローサイトメトリーへの応用
E. 赤血球の保存
7. 遺伝子の取り扱い
A. 多様な性状を持つ検体の前処理
B. PCR 阻害物質の除去
C. アンプリコン汚染の防止
D. リボヌクレアーゼによる RNA 劣化の回避
E. DNA 抽出の注意点
8. 血液ガス,電解質測定
A. 検査に用いられる検体の種別
B. 本項で想定した検体の種別と検査機器
C. サンプリング時の注意
D. 測定時の注意
9. 薬物濃度の測定
A. TDM における基本的知識・
B. 院内感染と TDM
C. 免疫抑制剤
D. 慎重な投与が必要な薬剤
E. その他
F. 有効域・中毒域について
第6章 内因性,外因性影響物質
1. 脂肪血症の影響:混濁した検体は測定に用いてよいか
A. 脂肪血症検体
B. 混濁の診断学的意味合い
C. 混濁による分析障害
D. 混濁に対する対策
2. 内因性抗体の影響
A. 寒冷凝集素
B. クリオグロブリン
C. EDTA 依存性抗体
D. 免疫グロブリン・酵素複合体(マクロ酵素)
E. 自己抗体
F. 異好性抗体
3. 溶血の影響
A. 溶血とは何か
B. 溶血の影響
C. 溶血の影響を如何に回避するか
4. 薬物による影響
A. 薬物による影響の機序
B. 薬物と蛋白質の結合
5. 検査前手順の品質保証
A. 検査手順の分類
B. 適切な検査前手順
C. 立場によって異なる品質保証の基準
D. 個別データの管理
E. 検査手順の時間管理
F. 検査前手順の適正化と手順書の作成
第7章 特定健診における検査前精度管理の在り方
1. 何故検査前精度管理が大切か
2. 検査前精度管理の問題点と改善策
3. 研究班での検討結果
4. コメント
5. 特定健診の実施における厚生労働省通知
6. おわりに
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:15.7MB以上(インストール時:34.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:62.8MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:22.7MB以上(インストール時:56.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:90.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784771950634
- ページ数:120頁
- 書籍発行日:2008年7月
- 電子版発売日:2018年7月27日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:2
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。