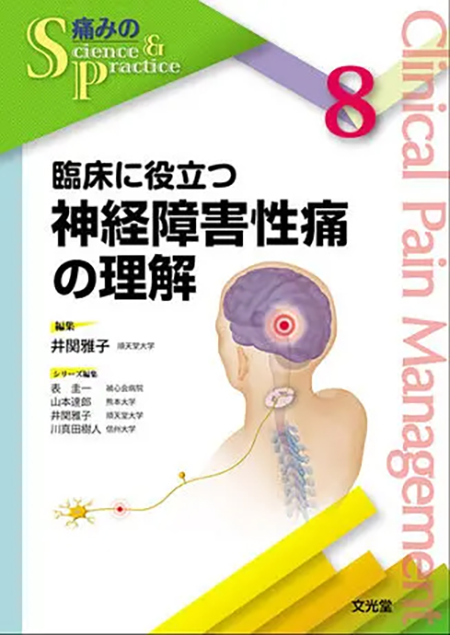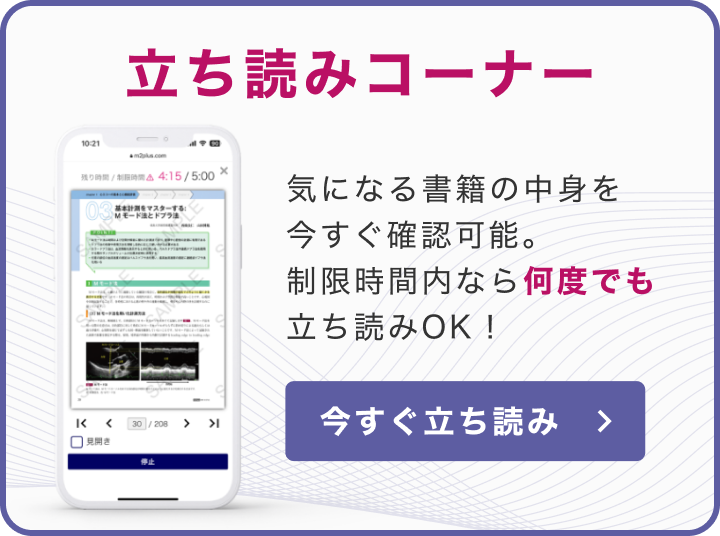- m3.com 電子書籍
- 川真田 樹人
- 痛みのScience&Practice 8 臨床に役立つ神経障害性痛の理解
商品情報
内容
神経障害性痛は長年注目され,多くの研究者や専門医により,様々な観点からの病態や治療法が探求されてきた.本書では痛み診療に従事する医師が最良の治療を行えるよう,「痛みの機序に関する基礎は,末梢から中枢まで連続性や統一性のある解説」「神経障害性痛の正しい理解のため,その要素を一部有している疾患やその周辺疾患も含めて解説」「各疾患については,疫学,病態,治療法などを詳細に解説」に重点を置き,実践的で分かりやすい構成を心がけた.
>『 痛みのScience&Practice』シリーズ
序文
最近痛みに関する関心が高くなってきています.また新たに多くの鎮痛薬が臨床で使用可能となり,治療手段も多岐になってきています.現在,痛みに関する書籍が多く出版されています.しかしながら,これらの出版物の多くが,痛みの治療法のガイドブック的なものであり,痛みに関する基礎的な生理学,薬理学,解剖学などに基づいた記述は多くないように感じています.また,痛みの治療を行う上級クラスの臨床医を十分に満足させる基礎と臨床がバランス良く記述された本格的な日本語の本は少ないのが現状です.そこで,今回麻酔科医を対象とした「痛みのScience & Practice」シリーズを上梓することといたしました.本シリーズは,麻酔科専門医およびペインクリニック専門医を目指す医師を対象としています.そしてペインクリニックを専門としない麻酔科医でも,痛みに関する正しい基礎知識に裏打ちされた,より良い診療の指針となるシリーズを目指しています.痛みに関する基礎的・臨床的知見は日進月歩です.本シリーズでは,最新の知見と治療法をまとめることを意図しています.そして痛み患者を診療するのに必要な基礎医学的知見と,エビデンスに基づいた治療を記載することを目指しました.このような気持ちをこめて,シリーズ名を「痛みのScience & Practice」と命名いたしました.
麻酔科はペインクリニック以外でも,手術時の痛みのコントロール・術後痛管理など,痛み治療にかかわることが多い診療科です.痛みをコントロールすることの多い麻酔科医にとって,「痛みのScience & Practice」は必読の書となると考えています.
1 冊250 ページくらいの書籍を,年に4 冊程度出版していく予定です.各巻の企画は編集者の1 人が作成した原案を,編集会議で何度も検討し,全員の納得が得られる状態まで練り上げました.それぞれの1 冊は,一つのトピックを多面的に理解できるよう編集しています.また,より理解しやすくするために多くのカラーイラストを入れています.
本シリーズは,多くの麻酔科医に新しい痛みの知見を紹介することができるシリーズとなっていると確信しています.本シリーズが今後の日本における痛み診療の発展に貢献できることを期待しています.
禎心会病院 表 圭一
熊本大学 山本 達郎
順天堂大学 井関 雅子
信州大学 川真田 樹人
国際疼痛学会(IASP)は,1994 年に"neuropathic pain(神経障害性痛)"を「神経系の一次的病変あるいは機能異常によって起きる疼痛」と定義した.この難解な痛みは大いに注目され,多くの研究者や専門医により,さまざまな観点から神経障害性痛の病態や治療法が探求された.その結果,近年では痛みの機序の解明が進み,治療法も豊富になってきた.
しかし,まだまだ,神経障害性痛は解決したわけではなく,痛みに苦しんでいる患者は各科に存在している.そこで,より多くの医師が最良の治療を行えるように,臨床医にとって,実践的でわかりやすい本をつくることを考えた.そのため,本書には,以下の3 つの特徴を持たせている.
第1 に,痛みの機序に関する基礎に関しては,末梢から中枢まで,連続性や統一性のある解説を心がけた.それにより,神経障害性痛の発生機序や生じた変化などについて,全体像が理解しやすい本となっている.
第2 に,本書では,あえて,神経障害性痛以外の周辺疾患も含めて解説している.神経障害性痛は,2008 年に「体性感覚系に対する損傷や疾患によって引き起こされる痛み」と再定義され,該当疾患も明記されているが,臨床においては,侵害受容性痛から神経障害性痛へ移行するような疾患,両者の特徴を持ち合わせた混合性痛など,幅広い病態を治療しているのが実情である.そのため,神経障害性痛の要素を一部有している疾患やその周辺疾患も含めて解説することは,臨床医にとって,神経障害性痛を正しく理解するためにも,非常に有用であると考える.
第3 に,各疾患について,疫学,病態,治療法などを詳細に解説している.近年では神経障害性痛に含まれるすべての疾患群に対して,同一の治療ストラテジーで臨む傾向にあるが,一方で各疾患に対する効率的な治療を行う機会を失っている危険性も否定できない.実際には,疾患により病態や予後は同じではないため,バックグラウンドの知識を本書により復習することで,各疾患また各患者に対して,より適切な治療を選択するスキルが身につくと考える.
本書は,痛み専門医から研修医まで,幅広い層の医師にとって,明日からの臨床に役立つ良書である.
2015年5月
順天堂大学医学部麻酔科・ペインクリニック 井関 雅子
目次
総説
神経障害性痛の疫学
解説
Ⅰ.神経障害性痛の発生機序
1 末梢性の機序
2 脊髄の機序
3 脳の機序
Lecture 動物実験から見た痛みと情動
Lecture グリアと神経障害性痛
Lecture Lysophosphatidic acid(LPA)と神経障害性痛
Lecture PACAPと神経障害性痛
II.診断・検査法
1 問診,理学的検査と知覚異常
2 画像検査:病態把握のための検査
1)脳機能検査
2)脊髄MRI検査
3 質問票:痛みの性状,神経障害性疼痛
4 質問票:不安,抑うつ,破局化,ADL,生活の質
5 電気生理検査
III.治療総論
1 薬物療法
Lecture TRPV1拮抗薬
Lecture Nタイプカルシウムチャネル遮断薬
Lecture サブタイプ選択的ナトリウムチャネル阻害薬
Lecture NMDA拮抗薬
2 理学療法
3 神経ブロック
4 脊髄刺激
IV.疾患各論
1 脊椎脊髄疾患
1)頚髄症
Lecture 頚部疾患のインターベンショナル治療
2)腰椎椎間板ヘルニア
Lecture 腰椎椎間板ヘルニアに対するインターベンション治療
3)腰部脊柱管狭窄症
Lecture 脊柱管狭窄症に対するインターベンション治療
4)腰椎手術後痛
Lecture FBSSに対するアプローチ法
2 帯状疱疹関連痛
Lecture 帯状疱疹痛に対する神経ブロックの有効な活用法
Lecture 帯状疱疹の痒み
3 糖尿病性ニューロパチー
4 複合性局所疼痛症候群
Lecture 骨折,捻挫後CRPS病態と予後,治療法
Lecture コンパートメント症候群の病態と予後,治療法
Lecture 血管穿刺後の遷延痛・CRPS病態と予後,治療法
Lecture CRPS発症早期/慢性期の理学療法
5 術後痛
1)開胸術後痛
2)鼡径ヘルニア術後痛
3)乳房手術後痛
6 三叉神経痛
Lecture 三叉神経痛の外科的治療法:適応となる病態
7 舌咽神経痛
8 脊髄損傷
9 幻肢痛
10 腕神経叢引き抜き損傷
Lecture 腕神経叢引き抜き損傷の脳神経外科治療:適応と有効性
11 胸郭出口症候群
Lecture 胸郭出口症候群患者の麻酔科的治療
Lecture 胸郭出口症候群の多様性
12 肘部管症候群
13 前骨間神経麻痺/後骨間神経麻痺
14 手根管症候群
15 梨状筋症候群
16 脳梗塞・出血後疼痛
17 パーキンソン病と慢性痛
18 多発性硬化症
19 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
20 化学療法に伴う痛み・しびれ(CIPN)の評価と治療
21 線維筋痛症
22 HIV関連神経疼痛
23 アミロイドーシス
Q & A
不動化により生じる弊害は?-基礎的見地から-
CRPSに対して交感神経ブロックは有効か?
CRPSに対する交代浴は有効か?
乳房手術後の諸症状に対してSGBは有効か?
鏡療法の適応と治療効果は?
パーキンソン病に対する脳深部刺激療法のタイミングは?
神経障害性痛の発生と症状に遺伝子多型は関与するか?
FBSSの中で腰椎再手術が適応となる病態とは?
生体内再生治療(in-situ tissue engineering)の適応性と有効性は?
痛みの難治化には,後生的遺伝子修飾(エピジェネティクス)が関与するのか?
難治化への分岐点とは?
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:113.1MB以上(インストール時:235.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:452.4MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:72.9MB以上(インストール時:154.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:291.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784830628405
- ページ数:300頁
- 書籍発行日:2015年5月
- 電子版発売日:2019年5月22日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。